| 2002年9月16日(月) ひょうたん(瓢箪)の大きな青い実。水筒にするコツは? 縁起がよい、福を呼ぶ、千成り瓢箪。ひょうたんの白い花と、小さな実 |
|
| ひょうたんの大きな実が、葉陰(はかげ)にぶら下がっているのを見つけました。 ●大宮八幡宮で、「菊被綿」を拝見した後、善福寺川(ぜんぷくじがわ)のあたりを散歩すると、まだ「青い実」ですが、樹木がいろいろと実をつけていました。  ←●ひょうたんの実です。 高さが21cm、上の丸みの幅が6cm、下の丸い幅が14cmです。 ●9月3日にのせた、武蔵五日市の巨大なひょうたんは、大きいですが、細長かったです。 ●今回のこのひょうたんは、いかにも、「むかしながらのイメ−ジ通りの形」をしています。 ●むかし話にでてくる、おじいさんが、腰に、ひょうたん(瓢=ひさご)をぶら下げ、そのひょうたんから、酒や水を飲むシ−ンが目に浮かびます。 ●「瘤とり爺さん(こぶとりじいさん)」や、「舌切り雀(したきりすずめ)」や「花咲か爺さん(はなさかじいさん)」達は、絵本では必ず、こういう形の茶色のひょうたんを腰にぶら下げて、かかれていました。 今の絵本では、いかがでしょうか? ●このひょうたんがもっと大きくなれば、たっぷりと、お酒も水も入り、「携帯水筒(けいたいすいとう)になるでしょう。 それにしても、水筒にする、コツと伝承される秘伝とは? ●ひょうたんの上部の「へた」に穴をあけ、水につけて中身を腐らせ、どろどろになった中身を、へたの穴から出し、空洞(くうどう)にする……そして干す………すると茶色になる…そうです。 …かんたんそうですが、ほおずきの実(7月12日エッセイ)を空洞にするのに、苦労したわたしとしては、「ひょうたんを水筒かわりにする技術」には、感嘆してしまいます。 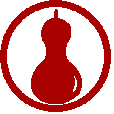 ●大小のひょうたんを沢山つけた「千成り瓢箪(せんなりびょうたん)」は、「縁起がよい、福を呼ぶもの」とされています。 ――なぜなら、足軽(あしがる)から、天下(てんか)をとった、豊臣秀吉(とよとみひでよし)の、旗印(はたじるし)だからです。 ●秀吉は戦い(たたかい)に勝つたび、小さいひょうたんを、1つずつ増やして、1000に成った……といわれています。 1 → 1000 ! 映画などで見ると、大きなひょうたんを中心にして、小さいひょうたんが、沢山ぶら下がっています。「千」というのは、言葉の彩(あや)かもしれませんが… 「千成(り)」という地名も、千成り瓢箪からきているのでしょう。 ●ひょうたんは、はじめ、まっすぐなキュウリのような実で、途中から、ウエスト部分がくびれてくるのかと思っていました。 人間は「幼児体型」の時は、ウエストのくびれはありませんし… ※→ウエストを細くする「ねじりのポ−ズ」は、『綺麗になるヨガ』 200p 『ヨガと冥想』 176p ビデオ『ヨガと冥想』 ●――ところが、ひょうたんは、小指の先ほどの小さいうちから、「ひょうたん型」↓にウエストがくびれているのです。  ●――それで、同じ「白い花」でも、「夕顔(ゆうがお)」の実とは、ちがう………「残念…」とわかるわけです。  ←●ひょうたんの「白い花」をまだ、先端に残して、ひょうたんの「青い小さな実」が、ふくらんでいるところです。→ ←●ひょうたんの「白い花」をまだ、先端に残して、ひょうたんの「青い小さな実」が、ふくらんでいるところです。→●NAYヨガスク−ルの生徒さんで、ひょうたんを手作りで「楽器」にして、「ひょうたん音楽」をご夫婦でなさっている方がいました。のんびりした暖かい音色(ねいろ)でした。 今は九州在住ですが、元気で、ゆったり、ひょうたんを奏でているでしょうか。 |
| ←★前へ | 次へ★→ |
 トップページへもどる
トップページへもどる
