
| ヨガと瞑想による「気づき」で、自分と世界が広がるフォト・エッセイ。こころ豊かに季節を感じる写真が大好評 |
| 2010年9月1日(水) ●ヨガと瞑想(冥想)で「じぶんの内部にはじめから、あるチカラを知り、気づく」そして「活用法を学ぶ」 ●セミ(蝉 せみ)の「第3の目」アジナ・チャクラ 緊急用の「キープ・パワー」すなわち「気とよばれる、生命エネルギー」チャクラ別のポーズなど『綺麗になるヨガ』のDVDは、『やせるヨガ』のタイトル ●「アスファルトへの筋目や網目のスタンプ」を「地球温暖化対策の温度を下げる、簡単なひと手間工夫」保湿性の緑の野草 ☆ど根性 植物☆ピンクのナツズイセン(夏水仙) ●東京・新宿の地産地消(ちさんちしょう)の内藤トウガラシ(唐辛子) ● 「ワルナスビ(悪茄子)」のトゲのすごさ ●「衆生済度の願い」で「即身仏(そくしんぶつ)すなわちミイラ(木乃伊)」になったお上人 ノウゼンカズラ(凌霄花) ●「昭和の花」黄色いカンナ ●綺麗なアゲハチョウ(揚羽蝶)のダンス ●正面からの赤トンボ(赤蜻蛉)の目や口は、まっ赤 ●「姿勢きちんと 通せんぼネコ」 ●水を通して見える、コサギ(小鷺)の足指は、黄色。 ●8月は戦後1946年以降、一番暑い夏 「やっぱり! 暑かった夏」 ●「できたての、こはく(琥珀)」のような樹脂が、光に輝く |
24節気の白露(はくろ) 9月8日 秋分(しゅうぶん) 9月23日 ●NAYヨガスク−ルの会員(生徒さん)のペ−ジ「猫の集会」の9月号をアップしています。 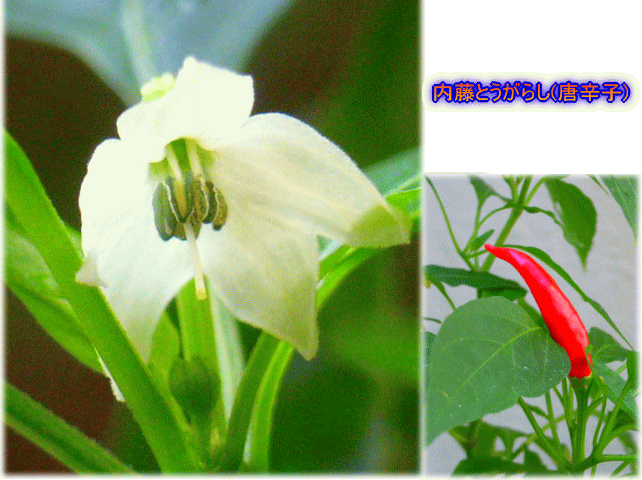 ●「やっぱり! 暑かった夏」でした。 データによれば、先月「2010年8月は、戦後1946年以降、一番暑い夏」でした。 体感温度として、異常に暑いとは感じていましたが、 じぶんが生まれてから、一度も記憶にないほど、もっとも暑い夏だったわけです。  ●そんな猛暑続きだったので、 「丈夫に育つか?」と心配していた「苗」が、 上や右の写真のように、 立派に花が咲き、右上の赤い実をみのらせてくれたのは、 とてもうれしいことです。 プレゼントしていただいた小さなポットに入った「苗」の名は、 「内藤トウガラシ(唐辛子)」です。 ●NAYヨガスクールのある、新宿は、むかし「内藤新宿」とよばれていました。 このあたりは、 江戸時代には、 まっ赤な内藤トウガラシ(とうがらし 唐辛子)が、たくさん実っていたそうです。 ●東京の「地産地消(ちさんちしょう)※」で、 「内藤新宿」の内藤トウガラシ(とうがらし 唐辛子) が、 残されていた[種]から復活されました。 それで、新宿の伊勢丹では、東京の「地産地消」を推進するため、 内藤トウガラシ(とうがらし 唐辛子)の苗を、 プレゼントするキャンペーンがあったそうです。  ↑MIYUさんは、2回並んで、「おひとり1鉢の苗」を、 ご自分用と、わたし内藤用に、計2鉢をゲットされました。 その、貴重な1鉢を、わたしにプレゼントしてくださいました。(感謝!です) ●その苗を、うちで育てたら、上の写真のように、 下向きに白い花が咲き、受粉すると、花はしぼんで茶色になり、 その下がふくらんで青い実になります。 そうやって、左のような青い実の内藤トウガラシ(唐辛子)が、 次々に実りつつあります。 1本だけ、すでに緑から赤になりました。上の写真。 江戸の色と味。 みんな赤くなるのを、楽しみにしています。 そろそろ、赤とんぼに出会う時季になりましたが、 赤いトンボのような内藤トウガラシ(唐辛子)にたくさん出会うのは、秋の終わりでしょうか。 ※「地産地消(ちさんちしょう)は、地域生産 地域消費(ちいきせいさん・ちいきしょうひ)の略語で、地域で生産された様々な生産物や資源(主に農産物や水産物)をその地域で消費すること」参考;Wikipediaより ●「赤とんぼ 羽根をとったら トウガラシ」 という残酷な(?)イメージの歌も、むかし流行しました。 猛暑のまっ盛りに、秋の気配の、 赤トンボ(赤蜻蛉)を見つけ、 正面から見つめあってしまいました。下の写真。 赤トンボ(赤蜻蛉)の目や口もとも、まっ赤です。 今年は、赤トンボ(赤蜻蛉)に出会うのが、早かったように思います。 ●赤トンボ(赤蜻蛉)の後ろからの写真とお話は、こちらへ。【2002年7月16日(火) 夏の盛りに、秋の気配。赤トンボ(赤蜻蛉) 昭和天皇の愛した武蔵野を残す昭和公園 5角形の紫のキキョウと、アメリカ国防省のペンタゴンの形 ヤントラ 五芒星 ★】  ●トンボ(蜻蛉 とんぼ)だけでなく、 蝶々も、猛暑の中、元気にとびまわり、 恐れる気配もなく、綺麗な羽根をみせてくれることが多かった夏です。 下は、目の前でピンクの花、ランタナ(7変化)の蜜をすう、 アゲハチョウ(揚羽蝶)です。 ふくらんだスカートから 細い脚がすっと伸びて、 ダンスをしているようです。 撮影してふりかえると、 「うまくとれました(笑)?」 と微笑むかたがいました。 邪魔にならないように、立ち止まって見守ってくださっていたようです。感謝!  ●こちらをみつめ続ける、綺麗なアゲハチョウ(揚羽蝶)の写真とお話は、こちらへ。【2003年7月30日(水) 「カメラ目線」で、こちらを見つめる、黒いシマ模様の白アゲハチョウ(揚羽蝶)。モンシロチョウ(紋白蝶)と紫色のサワギキョウ(沢桔梗)、ラベンダ−。目玉のような模様のジャノメチョウ(蛇の目蝶)。チョウ(蝶)をつかまえた後は? 映画の『コレクタ−』。チョウ(蝶)の羽化と「たましいの飛躍的な成長」を意味する「イニシエーション(通過儀礼 イニシエイション)」。 鳥のように「チョウ・ウオッチング」はいかが?】 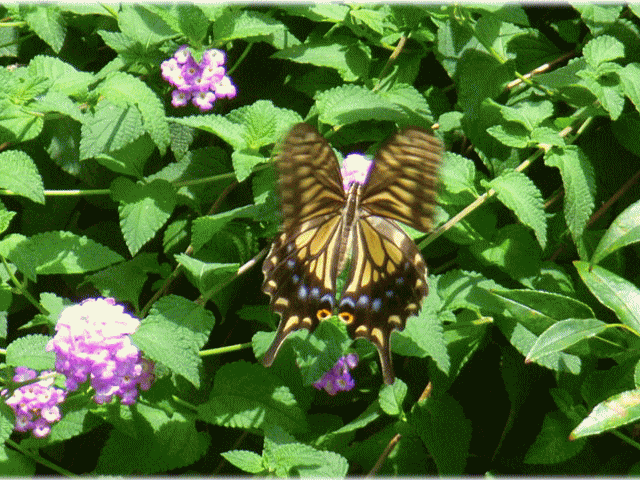 ● 24節気の白露(はくろ) 9月8日 白露(はくろ)は、「まわりの大気(たいき)が冷えてきて、水滴(すいてき)が、白露(しらつゆ)のように葉に宿りはじめる頃」 ●白露の時季に咲く花のお話と写真はこちらへ【2007年9月1日(土) 青紫の花 「言葉とヤントラ(マンダラ)の瞑想(冥想 メディテーション)」のページを更新。「2つでひとつ、集中力とリラックス 」。シラー(スキラ スキルラ:オウツルボ 大蔓穂)。紫の花 アゲラタム(郭公薊 カッコウアザミ かっこうあざみ)秋の七草の、フジバカマ(藤袴)に似る。 『源氏物語』の「夕顔(ユウガオ ゆうがお)の花は、かんぴょう(干瓢)の花」。白露の頃に咲く、小さな白い花】  ※24節気とは、太陰暦の時代に、太陽の運行(黄道)を基準に、1年を24等分し、季節の変化を知るために考案。1節気は約15日 ●この夏の暑さが、 性に合う(しょうにあう)花もあるようです。 上の黄色いカンナや、 下のオレンジのノウゼンカズラ(凌霄花)は、 生き生きと元気に咲いていました。 ●「昭和の花」のイメージで、花が大きめのカンナは、赤やオレンジもあり、 戦後すぐの小学校の校庭によく咲いていました。 見かけるたびに、毎年、撮影していましたが、うまくとれません。 というのも、花が上下にいくつも咲くので、 すべてが美しい状態をとらえるのがむづかしいからです。 今回は、2ヵ所で撮影した黄色いカンナです。 ロート状の花の内部のオレンジ色の斑点が、虫を呼ぶ装置らしいです。  ●秋分(しゅうぶん)が 9月23日。 秋分は、「24節気の1つで、太陽が黄道(太陽の道)の<秋分点>にきたとき。 お彼岸のお中日(おひがんのおちゅうにち)」。 ●秋分 の時季に咲く花のお話と写真は、こちらへ【2003年9月24日(水) 秋分は、天球で「春分点」の反対側に太陽がきた日。『万葉集 』で、山上憶良が「萩の花 尾花 葛花 なでしこが花 をみなへし また藤袴 朝顔が花」と、「秋の七草」をよむ。「春の七草」の歌との口調(リズム)のちがい。(5・7・7)×2と(5・7)+(5・7・7)。こころをうたう「定型詩の形」の変化は「呼吸のリズム」のちがい? オミナエシ(女郎花)とオトコエシ(男郎花)の花】 ●暑い中、こころ寒い話が、続きました。 親をミイラにして、年金を詐取…の「現代版 怪談」を皮切りに、 続々と「100才超えた行方不明の高齢者」が、出現(?)・・・ 日本は、ほんとに「長寿社会」なのでしょうか? ●「ミイラ(木乃伊)」といえば、暑い夏に東北へ旅行し、 オレンジ色のノウゼンカズラ(凌霄花)がみごとに咲いていたお寺を思い出します。 「苦しんでいる多くの人たちを救いたいという、 衆生済度(しゅじょうさいど)の願い」から、じぶんから食を断ち、 「即身仏(そくしんぶつ)すなわちミイラ」になった、 お上人(しょうにん)様。 その即身仏のミイラは、「のんの様」とよばれて今でも慕われていました。 拝観したお上人(しょうにん)様のミイラを守っているのは、 ブルーの目のシャム猫でした。 ●今年は、あのお寺で見たように、オレンジ色のノウゼンカズラ(凌霄花)が、 太陽の光を受け、あちこちで元気に咲いていました。下の写真2枚。  ●ノウゼンカズラ(凌霄花)は、ツル草なので、どの木にからみつくか、 によって、ちがう姿の花木のイメージになります。 下の写真は、左右の木がちがうので、 「2種の葉をもつ、ノウゼンカズラ(凌霄花)の木」に見えます。 ●日本の「ミイラ(木乃伊)」と「即身仏」そして「即身成仏」、ノウゼンカズラ(凌霄花) の写真とお話は、こちらへ。【2003年7月26日(土) お寺のガラスケ−ス内の「即身仏、すなわちミイラ」を拝観した時、庭に咲きこぼれていた、オレンジ色のノウゼンカズラ(凌霄花)。真夏の東北旅行の思い出。冷害になりそうな今年、五穀断ちしてミイラ(木乃伊)になったノンノ様、お上人(しょうにん)の願いを思う。即身成仏(そくしんじょうぶつ)とは】 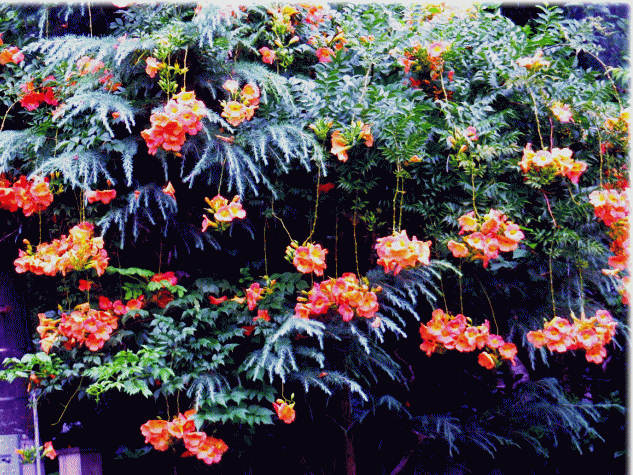 ★ど根性 植物★ シリーズ その4 「変則的な状況でも、しっかり元気に生えている草花(くさばな)たち」を紹介します も しも、同じような「厳しい状況」におかれているかたがいらして、 この「小さな生きもの達」の勇気と元気にふれて すこしでも、共感(シンパシー)を感じ、同じ生きものとして、 【閉塞状況でも、へこたれず、 たくましく生きぬく力】がわいてきたらうれしいです。 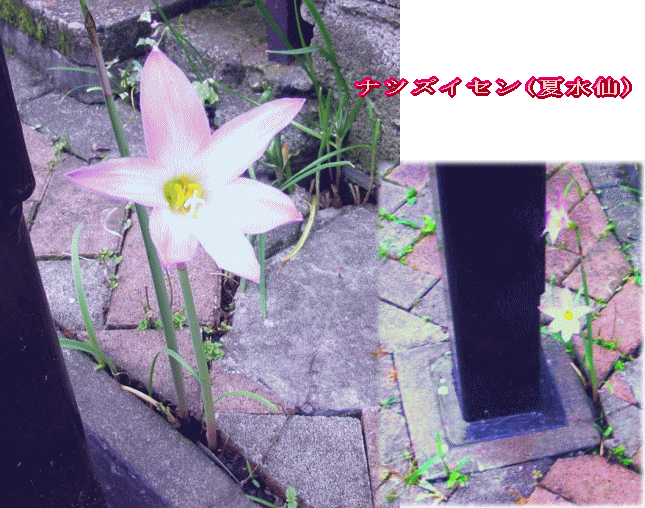 ●猛暑の午後、1センチほどのすき間(ニッチ)に、 茎をまっすぐに伸ばした、2輪のピンクの花が咲いていました。 高さは、30センチ前後です。 まるで、そばの電柱と競うように、すっくと伸びている花。 ほかの緑の[植物]たちは、くたっとしている暑い日なので、 この5センチほどのピンクの花は、目立ちました。 ●マンジュシャゲ(曼珠沙華 まんじゅしゃげ)と同じ、 ヒガンバナ(彼岸花 ひがんばな)科のナツズイセン(夏水仙)です。 別名は、リコリス。 ●ヒガンバナは、【[根っこ]の根茎】で増えるので、 どこかの花の[根っこ]が、 この敷石の下を通り、小さなすき間(ニッチ)から 2輪のピンクの花を開かせたのでしょうか。 ――まさに「☆ど根性 植物☆」です。 ●暑い夏に出かけた山国の水車のそばで、たくさん咲いていた このナツズイセン(夏水仙)を思い出しました。 暑い夏の太陽の下で、涼しげに咲く、ナツズイセン(夏水仙)です。 ●ナツズイセン(夏水仙)と水車小屋の写真とお話は、こちらへ。【2006年9月1日(金) ●「どっちが自分?」という「新しい自分」への「脱皮」は、「アイデンティティ・クライシス(自我の危機)」 ●「夕暮れのセミ(蝉 せみ) の脱皮」を見た! アブラゼミ(油蝉 あぶらぜみ)とヒグラシ(蜩 ひぐらし)。 ●虫の抜け殻 バッタ(飛蝗 ばった)? ●国蝶 オオムラサキ とクワガタがいっしょに樹液を吸う。●ナツスイセン(夏水仙 なつすいせん)は、ピンクの花、 ヒガンバナ(彼岸花)の仲間。 ●水車(すいしゃ)と青田(あおた)。● 「招福開運 空と雲のシュリー(女神)ヤントラ akiyo作 」 秋風(あきかぜ)が身にしみるメランコリー(憂鬱 ゆううつ)ウツ症。 ●精神科医に扮したラジニカーントの2005年の最新作、おすすめインド映画。「チャンドラムキ 踊る!アメリカ帰りのゴーストバスター」インドの「シヴァ派の行者」は、「チョークで床にかいたヤントラ(マンダラ)」の上に「悪霊憑き」をすわらせ、悪霊を払う】  ●上は、東京も38度になった猛暑日に、 とけそうなアスファルト道路のすき間(ニッチ)にはえていた草です。 通行人に踏まれるし、アスファルトは焦げそうに熱いのに、元気な草たちです。 ●犬達ですら、アスファルトは焦げそうに熱いので、散歩をしない時間です。 焼けこげたり、、枯れたりせずに、草の緑を保っているのが、すごいです。 「保湿成分」がたっぷりとあるのでしょうか。  ●小さな草の名まえはわかりません。 武蔵野の草花を愛した昭和天皇によれば、 「名のない草などなく、名を知らぬだけ」です。 ●ホースで水をまいても、 すぐに「焼け石に水」状態のアスファルト道路。 水をかけると、焦げた臭いがシューッという音とともにします。 ☆★☆そんなとき、必ず思うのは、 「アスファルトを敷いたら、最後の仕上げに、 《縦(|)(横―)の筋目や、格子縞+++》 の「網目(あみめ)をプレスしてほしい!」 ということです。 そうすれば「敷石」のすき間(ニッチ)と同じに、 コールタールのまっ黒なアスファルトにも、すき間(ニッチ)ができます。 ※このイメージとしては、禅寺で数百人分の焼き物などをつくるとき、 「1度にたくさん《焼き目がつく巨大スタンプ》のようなものを押す料理場面」を、 みたことがあるからです。 ☆★☆アスファルトにも、「筋目の大スタンプ」を押せば、ほっといても、 野草がすき間(ニッチ)にはえるようになります。 それなら、もっと涼しくなるのに! と思います。 野草も必死に、水分を保湿するし、陣地(?)を増やそうとするでしょうし。 ☆★☆ゴーヤ(レイシ 茘枝)や、ヘチマ、ヒョウタン(瓢箪)などの ツル草による下から上へ伸びる「緑のカーテン」は、あちこちで見られるようになりました。 今度は、足もとの「アスファルトへの筋目や網目のスタンプ」 を「地球温暖化対策の温度を下げる、簡単なひと手間工夫」 として、お願いしたいですね。 もちろん、それぞれの「駐車場のコンクリート」にもお願いしたいです。 夏の車は、「鉄板焼き」状態ですから、コンクリート地面のすき間(ニッチ)に、 野草があったほうが、涼しいのではないでしょうか? 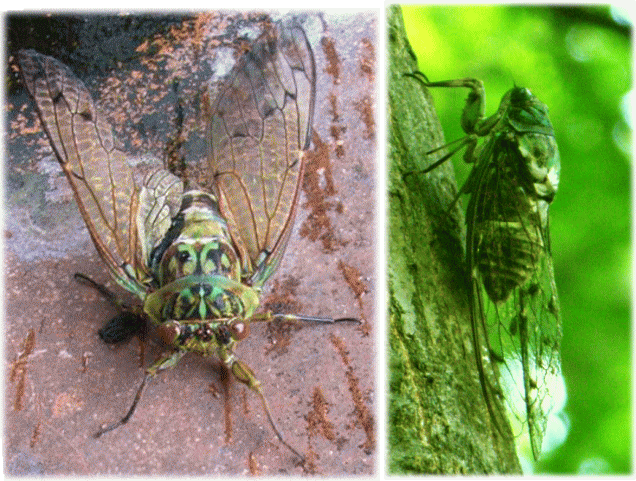 ●今年は、セミ(蝉)のなくのが遅い、と先月の「フォト・エッセイ」にかいた翌日から、うるさいほどセミ(蝉)の鳴き声がするようになりました。 暑いせいか、昼は静かで、夜、鳴く声も、よくききました。 ●下の白鷺(しらさぎ)に会った、暑い日、自転車をおりて、 涼しい公園を散歩すると、目の前に、羽根を広げたセミ(蝉)が落ちていました。 透き通った羽根のヒグラシ(蜩)です。 踏んづけられるのは可哀想なので、ひろって草場の陰においてやろうとすると、 指にしがみついてきます。 まだ、生きている。 そして、茶色の丸い目玉の中の黒い小さな瞳で、こちらをみつめます。 ●緑の草の中におこうとすると、そこから土に落ちます。 ――何度かくりかえし、結局、水をふくませれば元気になるかな、 と水飲み場へ、つれていきました。 しかし、水は飲まず、こちらへ寄ってきます。 目線は、しっかり、こちらを見て、 おでこの「第3の目」のあたりの「赤い粒(つぶ)」が、光ります。 ●3つの粒が三角形▽をつくり光を受けて、輝いている写真が上の左です。 (右は、別の日、別の元気な、ヒグラシ(蜩)の写真です。) ●セミ(蝉 せみ)の「第3の目」の写真とお話は、こちらへ。【2004年8月2日(月) 葉月(はづき)。昨夜は、満月。セミ(蝉)の目と目のあいだに、小さな赤いルビ−のような透明な粒が2つ、キラキラと太陽の光に輝いて、とても綺麗。カメラ目線でこちらをみつめるアブラゼミセミ(油蝉)】 ※後記:目のあいだの赤いルビ−のような粒は、「個眼」といいいます。2つの目が、「複眼」。そのほかに「個眼」が、あるそうです。詳細は、こちらへ。【2004年8月8日(日) 立秋。残暑見舞い。黄色い縞のトンボは「ムカシヤンマ」ではなく、オオシオカラトンボのメス。♀。アブラゼミの目(複眼)のあいだの赤いルビ−のようなものは、「個眼」という目。眉間の「第3の目」と冥想(瞑想)。涼しい日陰に咲く、ヤブミョウガ(藪茗荷)、別名フラワ−ジンジャ−の白い花は、ツユクサ(露草)科。2つ重なって咲く、青いツユクサ(露草)の花】 ☆★☆おでこの「第3の目」のあたりは、人間でいえば「アジナ・チャクラ」です。 昆虫のセミ(蝉)にも、「チャクラ」があるかどうか、はわかりませんがませんが… 人間もセミ(蝉)も、「同じ、生きもの」として、 「気とよばれる、生命エネルギー」をもっています。 そして、ピンチになると、緊急用の「キープ・パワー」が、放射されます。 その緊急用の「キープ・パワー」に関連した、ツボ(急所)が「チャクラ」です。 ★ピンチのセミ(蝉)をひろうと、よく、「第3の目」のあたりの粒が光ります。 そして大きな鳴き声をだして飛び去るセミ(蝉)もいました。 ★このヒグラシ(蜩)は、歩けるようになったし、 ピカピカと「第3の目」のあたりの粒が光り、近づいてきます。 ★しかし、用事もあるので、また、緑の中に、おきましたが、 また、葉から「下りて」、動きまわっていました。 飛べなくても、天寿をまっとうしてほしい。。。とその場を去りました。 ☆★☆セミ(蝉)だけでなく、わたし達・人間には 「気とよばれる、生命エネルギー」だけでなく、 緊急用の「キープ・パワー」や「潜在能力」があり、「チャクラ」もあります。 しかし、「気づいてない」ことが多く、 逆に、破壊的だったり、自虐的だったりと マイナスに「気やパワー」を使っていることが多いです。 まず、「じぶんの内部にはじめから、あるチカラを知り、気づく」 そして、その「活用法を学ぶ」。 それが「ヨガと瞑想(冥想)」です。 ●緊急用の「キープ・パワー」や「潜在能力」と「チャクラ」についてのお話は下記へ。 ・『綺麗になるヨガ 心とからだを波動から美しく』 本は、こちらへ。↓ ・『ヨガと冥想』 ■ネット書店 ◎DVDは、NAYヨガスクールの通信販売です。こちらへ。  ●いつもの川で、コサギ(小鷺)をみかけないので、猛暑をさけ、 「河岸(かし)を変えた」のかな、 と思っていました。 ●別の川へ自転車で出かけた、 ある猛暑の日。 川底を、黄色い足で、 ゆっくりと、踏みしめながらあるいている、 白鷺(しらさぎ)に会いました。 クチバシは黒で、足指(?)は、黄色。 コサギ(小鷺)です。 見られているのに慣れていて、カメラを向けても逃げずに、炎天下で、漁をしています。 下の水が鏡になり、白い姿をうつしています。 ――あの、いつも見ていたコサギ(小鷺)かな、と思いますが、どうでしょうか・・・ ●コサギ(小鷺)の写真とお話は、こちらへ。【2003年12月29日(月) 金星(ビ−ナス)が輝き、土星(サタ−ン)が正月の1月1日には、30年ぶりに最接近。1年で一番綺麗な東京の星空。初雪の翌日、シラサギ(白鷺 コサギ)に会う。「忙中 閑 あり」。「接近遭遇」を、距離感をもち、水面を波だてないようにして、迂回する、渡り鳥のオナガガモ(尾長鴨)夫妻 】 ●このところ、ご自分の「ココロとカラダと気分」の「なんとなく、のリズム、調子」は、 いかがでししたか? ●台風のシーズンで、低気圧が近づくと、 不機嫌になったり、イライラ、むしゃくしゃしたり、 頭痛がするかたがいます。 気圧の変化に、体や気分が無意識に反応しているのでしょう。 まずは、お腹に手を当て、 深く息を吐いて、次に静かに吸う、腹式呼吸法をして、 気分をきりかえましょう。 気を腹に、まずしずめ、 お腹を「熱」に、あったかくしましょう。 次に、体を流れる気が、 上中下に、「冷-暖-熱」の温度差になっているように、気の波長を整えましょう。 気持ちが落ちつき、心と体の調子も整います。 ●深い腹式呼吸や、「 冷-暖-熱」の瞑想(冥想)は、以下をどうぞ。 ・本 カラーでわかる『ハッピー体質をつくる3分間瞑想』を。こちらへ。 ■ネット書店: ◎DVDは、NAYヨガスクールの通信販売です。こちらへ。  ★「見ている猫(ネコ)」シリーズ、その21 はじめて通る道で、横道(よこみち)があるので、 曲がろうとしたら、「先客(せんきゃく)」がいました。 前足をそろえて、きちんと座り、こちらを見すえる白と茶の猫。 おでこから鼻筋そしてほほから、胸、両足と、きれいな白で、首輪をしています。 (ここは、行き止まりです。) と、強い目の光りで、伝えてきます。左の写真。 ――たしかに、袋小路(ふくろこうじ)になっていました。 きりっとした顔が可愛いので、近寄って、写真をとろうとすると、 目はこちらをむいたまま、身動きします。 両耳が緊張しています。 (これ以上、くると、逃げちゃうから) と左へ体勢をすこし変更。 ――結局、見つめあったまま、撮影させてもらうことにしました。 「姿勢きちんと 通せんぼネコ」と名づけた、暑い日でした。 ●NAYヨガスク−ルの会員(生徒さん)のペ−ジ「猫の集会」9月号をアップ。こちらへ。 ●MAMI さんは「世界遺産 エステ家別荘 イタリア、ティヴォリ 2」。どの噴水も涼しげ。 ●Tomiko さんは「下田太鼓祭り 」。 ●美樹さんは「長野・西方寺のチベット大仏」。製作途中は、こんなかんじですか。 ●MIYUさんは「つばめの巣立ち」。盆提灯が涼しげ。 ●Kayokoさんは「チアリーダー ダンスフェスティバル」。はじけてます! ●yosihiroさんは 「きいちご」。 ●まどかさんは、エッセイ「中華三昧」。鍋の熱さ! ●mariko さんは「うちの猫」。太陽の光がまぶしい。 ●シンゴさんは、<Living>13曲目、「朝」。物語を感じました。 ●Tadashiさんはトルコ「カッパドキア 2」。内部には、イスラム教徒から隠した「壁画」…。 ●Ryoさんは「 斜め・カーブ・直線」@浅草 。後ろに見えるのは・・・ ●健治さんは「私の居場所」。 ●和之さんは「はじまりの水」。42回目。やっと「はじまりの水」をくむと・・・。  ●透明な樹脂に、太陽の光があたって、「燃える火」のように、 輝いていました。 まるで、おいしそうなジェリーのようです。 こはく(琥珀)に似ていますが、 さわると、ぷるぷると、やわらかい。 「できたての、こはく(琥珀)」のようなものなのでしょう。 モモ(桃 もも)の木にできていた、樹脂です。 左端に、小さなモモ(桃)の青い果実があります。 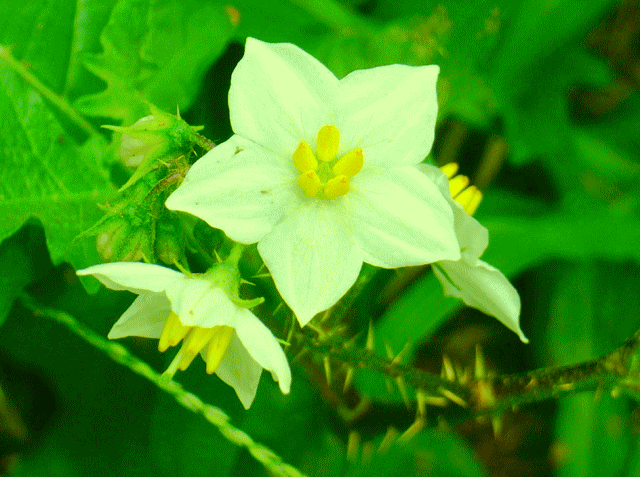 ●「ワルナスビ(悪茄子)」のトゲのすごさの片鱗でも見たい、 という先月の写真へのご要望に、おこたえして、上の写真をどうぞ。 花や葉、茎にもトゲがあり、細いので、逆に肌をさし、痛いそうです。 ●発見者で、名付け親は、あの植物学者の牧野 富太郎さん。 彼が、ぬいてもぬいてもはえてくると嘆いていたそうです。 ぬいても、根の切れはしが少しでも残っていると、そこから再生するそうです。 細かく切ると、そのすべてから再生する、海のヒトデのように、生命力が強い、[植物]です。 ●「悪」という言葉には「強い」「猛々(たけだけ)しい」という意味もあります。 歴史に名を残す、 「悪源太(あくげんた)」とよばれたのは、源氏の棟梁である源 義朝の長男で 「源 義平(みなもとのよしひら)」です。 「悪源太 義平」として、歴史に名を残しています。 再来年のNHK大河ドラマは「平 清盛(たいらのきよもり)」だそうです。 そのラスト近くには、平家滅亡の話とともに 「悪源太 源 義平」が、多分、出てくるのではないでしょうか。 ---------------------*--------------------------*---------- *-------------------------------* ●「nature photo」更新しました。 ◆2010年 8月分は、こちらへ。 ●9月分は、こちらへ 10.8.29● 赤紫のムクゲ(木槿)の花の中に、黄緑のメジロ(目白)が! 珍しいツーショット。 白いクサギ(臭木)の花は、甘い香りで、たくさんの蝶々をさそいます。 黒い蝶々は、クロアゲハ(黒揚羽)だけでなく、ナガサキアゲハ(長崎揚羽)なども。 南の蝶々、赤星ゴマダラは、東京に定住化が進行中。 10.8.23● たくさんの白いレースのようなカラスウリ(烏瓜)の花、 たくさんの揚羽蝶(ハゲハチョウ)の群れ・・・ とても幻想的でリッチです。 真夏のカルガモ親子のそれぞれの家族も、それぞれに可愛いです。 10.8.15●珍しい蝶々、ジャコウアゲハ(麝香揚羽)は、「毒をもって、毒を制す…」 キバナ(黄花)コスモスには、ヒメアカタテハ(姫赤立羽)がよく似合う… 白蓮の開花、ピンクのハス(蓮)の花と、葉の露が涼しげです。 ヤマボウシ(山法師) 別名:ヤマグワ(山桑)の赤い実ができつつあります。 あの「エラソウな」ツバメのヒナが巣立ったようです。黄色いクチバシがご愛敬。 10.8.9● 立秋(8/7)をすぎ、いろいろな青い実がなりはじめています。 丸いキカラスウリ(黄烏瓜)、細長いカラスウリ(烏瓜)、そしてヒョウタン(瓢箪)の実! くちばしの黄色いツバメ(燕)のヒナが、「上から目線」で、エラソウになってきました。 ハチ(蜂)に擬態する、オオスカシバの羽根は透明な透かしで、宙に浮いたよう。 10.8.1● 夏空に咲く、花木が元気です。オレンジ色のノウゼンカズラ(凌霄花) ピンクのサルスベリ(百日紅) 白いエンジュ(槐)の花 夏の赤い実サンゴジュ(珊瑚樹) 同じアオイ科のピンクのフヨウ(芙蓉)と5裂の葉が涼しげな、赤いモミジアオイ(紅葉葵) 2匹のアゲハチョウ(揚羽蝶)のダンス |
 『家庭でできるビュ−ティ「ヨガ」レッスン』 『家庭でできるビュ−ティ「ヨガ」レッスン』 内藤景代・著 PHP研究所・ \1300 「体に効く、心に効く、美に効く」ヨガを、見開きの2色の図解のイラストで。呼吸法と「気の流れ」もわかりやすいと大好評! ★表紙の拡大イメ−ジ★内容のご紹介●目次のご紹介■ネット書店 ●韓国版・翻訳 |
 新版『BIG ME』大きな自分に出会う こころの宇宙の座標軸 新版『BIG ME』大きな自分に出会う こころの宇宙の座標軸内藤景代・著 NAYヨガスク−ル刊 ★「BIG ME(ビッグミ−)って、何?」は、こちらへ★ お求めは、通販をご利用ださい。¥1.200(税・送料込み)こちらへ。 |
 戻る
戻る


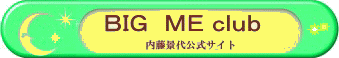
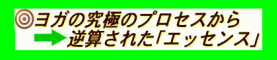






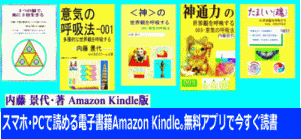
.gif)