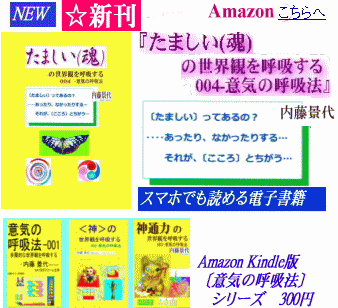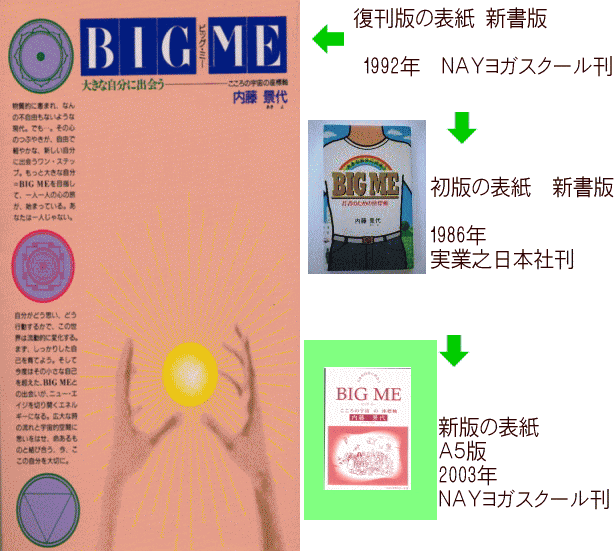2002年11月9日(土)
|
| 「寒暖の差」が激しいほど、綺麗に紅葉するといいわれます。 「急に、寒くなったな〜」と感じる時、紅葉作戦(?)が進行中なわけです。今、あちこちのおうちの、ふだんは目立たない地味な生け垣(いけがき)が、紅葉(こうよう)しています。 夏の間、涼しげだった、緑のツタ(蔦)も、紅や黄色に「こうよう(紅葉、黄葉)」しつつあります。 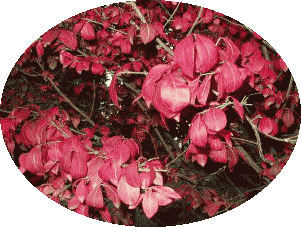 ●紅葉した葉  ●ツタ(蔦)もみじ ●…そういえば、「秋」という字は 「ノ 木(のぎへん)」に「火」です。 緑の木々におおわれた山に「火」がついて、 紅く燃(も)えたつように色どる、 紅い葉は、「紅葉=もみじ」というわけです。 秋 = 木 ノ + 火 ● ♪♪ 山が燃える……♪ は、『天城越え』 『燃える秋』は、五木寛之・著 『紅葉の美学』は、栗田 勇・著 上記の作品は、 どれも「日本の秋」のイメ−ジです。 中国の漢字の「秋の語源」は、知りませんが… 中国の「陰陽五行(いんようごぎょう)」の 「5色」の考え方では、「赤い」のは夏で、 「朱夏(しゅか)」といいます。 秋は、「白」で、 「白秋(はくしゅう)」といわれます。 叙情的な詩人の 「北原白秋(きたはらはくしゅう)」というペンネ−ムは、 ここから名づけたとききました。 ※→朱夏、白秋、そして青春については、『BIG ME』 202p を。 ●さて、日本では、 紅く燃えたつような紅い絹を、 「紅絹(もみ)」の布地(ぬのじ)といいます。 「紅絹布(もみぎれ)」ともいいます。 紅い絹 = 紅絹 = もみ = 火のように燃える紅 ●そういう発想でいくと、 桜もみじだけでなく、 ツタ(蔦)もみじ、 柿もみじなど、 いろいろな紅葉した葉も「もみじ」とよぶわけです。 けれども、 「猫じゃらし(エノコログサ)」など、ふつうの葉の紅くなったのは、 「紅葉(こうよう)」とよび「紅葉(もみじ)」とは、あまりよばないようです。  ●ツゲ(柘植)の生け垣の紅葉 ●外部から家をへだてる塀(へい)のかわりの生け垣にも、 紅葉しているものが、あちこちにあります。 ●母の遺品に、たくさんの数10cmの「紅絹の布地」が、 洗い張り(あらいはり)されて、束ねられていました。 わたしをふくめた子ども達の着物をほぐしたりして、 集まった裏地(うらじ)の紅絹のようです。 「紅絹裏(もみうら)」といっていました。 ●古代には「絹の道(シルクロ−ド)」、 明治時代は原 三渓さんが、絹の貿易で巨富をえたように、 絹は貴重品でしたから、 明治生まれの母は、 また何かに紅絹を再使用(リサイクル)の予定だったのでしょう。 誰か若い人の着物のすその裾回し(すそまわし)の蹴出し(けだし)に、 「紅絹裏」として使うつもりだったのかもしれません。  ●歩くときに、チラリと、 すそから着物の「紅絹裏」が見える裾捌き(すそさばき)に、 ハッとする「色気(いろけ)」を感じた時代があったのです。 今は、歌舞伎や映画などの お芝居の世界に残るくらいでしょうか… ↑●生け垣の紅葉 ●きのう、地下鉄で座っていると、 前に立った女性の ――洗いざらしのブル−・ジ−ンズ地の ――ミニスカ−トは、太ももの中程あたりの丈の「超ミニ」で、 もっと上に2ヶ所、5cm四方の穴が破けて(破いて?)あり、 目のやり場に困り …見てしまいました。 こういう露出度の高い時代には、 「紅絹裏」が見えるか見えないか …が重要ポイントの美意識は、 ほとんど理解不能ではなかろうか? と愚考いたします。 ●着物の再利用の習慣は、 むかしは当たりまえだったようです。 以前、秋の京都へ行ったときに、 紅葉の美しい洛北(らくほく)の 嵐山(あらしやま)近くの 北野天満宮(きたのてんまんぐう=てんまぐう)で、 古着市(ふるぎいち)をしていて、 着物だけでなく、むかしの布地も売っていました。 外国人客も多く、大規模で、 さすが、祇園(ぎおん)のある京都‥‥と思いました。 ●ところが、最近は、NAYヨガスク−ルの近くの新宿の花園神社でも、毎週日曜日には、古道具市や古着市を開いていています。着物や古時計などもあり、「タイム・トリップ」してしまう、懐かしい品がたくさんありました。 明日 2002年11月10日は、NAYヨガスク−ルの、 月1回 第2日曜日 午後 1:00からの内藤景代の総合クラスです。 |
| ←★前へ | 更新記録 | 次へ★→ |
 トップページへもどる
トップページへもどる

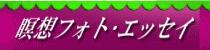
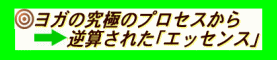 〔3時間で5,000円 〕会員は4,000円
〔3時間で5,000円 〕会員は4,000円