| 2003年4月17日(木) ●黄、紫、白、ピンク、オレンジなどのカラフルな組み合わせの三色スミレ(パンジ−)の鉢植えが咲いています。 ●芭蕉が俳句によんだ「すみれ草」は、別名を遊蝶花という 三色スミレ(パンジ−)ではありませんでした ●山路(やまじ)来て なにやら ゆかし すみれ草 松尾芭蕉 ◆『三色スミレ』 = 『野生の思考』 |
| きょうは、満月。 ●きのう、紫色の濃淡の花「日本に自生している、野生のスミレ」を お見せしましたが、 西洋の「野生のスミレ」は、黄、紫、黒の3色の 「三色スミレ(パンジ−)」の原種だそうです。 ●冬でも日本で咲いているのは、 園芸種の「三色スミレ(パンジ−)」です。 ●いかにも、三色スミレ(パンジ−)らしいのは、 花びらが2色の組み合わせになっている花です。 その色は、白、ピンク、オレンジ、藤色、薄紫、濃紫 そして黄、紫、黒の組み合わせですから、多様になります。 「順列組み合わせ」はいくつ?  ●三色スミレ パンジ− ●三色スミレ(パンジ−)といっても、 上記のうちの、「1色だけの花」もあります。 それをそれぞれのおうちで、組み合わせ、並べて 「寄せ植え」にしたりして、独自性を出しています。 ●三色スミレ(パンジ−)は、 江戸時代には日本には知られていませんでした。 明治時代に、日本に輸入され、 大きな丸い花びらを「胡蝶(こちょう=蝶々)に見立てたのか、 「遊蝶花」と名づけらたそうです。 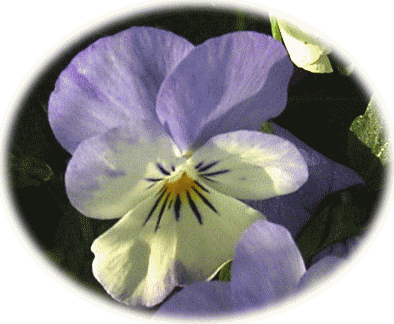 ●丸い花びらの三色スミレ(パンジ−)のほうが、 今の日本では「一般的」で、よくみかけるスミレになっているようです。 ●それしか見たことが、ない…というかたも多いでしょう。 かつてのわたしのように。 ●パンジ− 三色スミレ↑ ●だからといって、 江戸時代の芭蕉(ばしょう)が「ゆかしい」と、 俳句によんだ「すみれ草(スミレ 菫)」を、 三色スミレ(パンジ−)とイメ−ジして想像すると、 「ズレた光景」になってしまうでしょう。 山路(やまじ) 来て なにやら ゆかし すみれ草 松尾芭蕉 ●『源氏物語』の小さな白い夕顔(ユウガオ)の花を、 大輪の白い夜顔(ヨルガオ)の花…… と思っているよりもっと、 「時代の感性(センス)に、ズレ」があるようです。 平安時代の貴族の好む「白い花」と、 現代人に人気の「白い花」は、ちがう… 「白い花」を求めての、このお話は、 去年の夏、長い「続き物」になりました。 ●さて、三色スミレ(パンジ−)のパタ−ンから、 「野生の思考」の「形(構造)」を、発見したのが、 文化人類学者のレヴィ・ストロースです。 それで、レヴィ・ストロースは、 フランス語で『三色スミレ』という題(タイトル)の本をかき、 「構造主義」の名著として有名になりました。 彼の『三色スミレ』という本は、 日本語で『野生の思考』と訳されています。 『三色スミレ』 = 『野生の思考』 ●パンジ−(三色スミレ)のような『野生の思考』とか、「構造主義」とは? また明日、 カラフルな三色スミレ(パンジ−)の写真とともに、お話しましょう。 |
| ●「内藤景代の本 心に残る言葉」 読者とつくるページです |
| ←★前へ | 更新記録 | 次へ★→ |
 トップページへもどる
トップページへもどる
