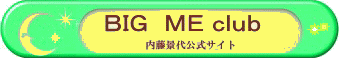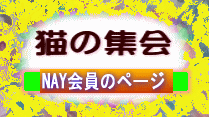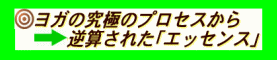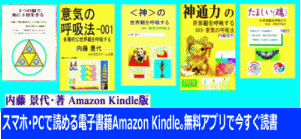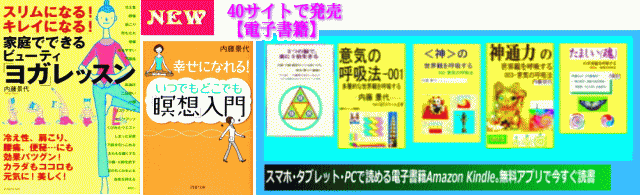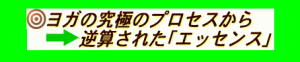トップページへもどる
トップページへもどる | BIG ME club | 内藤景代が毎日更新する 日誌風エッセイ 最新情報 |
| 2002年7月22日(月) ●私とは、何か?=Who am I ? ●『わたし探し・精神世界入門』と、 埴谷雄高の『死霊』の 「自同律の不快」のつながりぐあい。 ●「自分がイヤ……私 ≠ 私 A ≠ A 」と論理学。 ●精神のリレ− ◎スヌーピー 犬になりたくなかった犬 |
|||||||
☆[科学的思考法]=論理学の基本(A = A)が土台 →自同律=同一原理 princeple of identity =I D アイディ (→アイデンティティ) ☆「自分がイヤ……私 ≠ 私 A ≠ A 」と論理学。 ◎犬であることがイヤ(→ スヌーピーの人気 ●『わたし探し・精神世界入門』内藤景代・作 Who am I ? |
|||||||
…きのうの、つづきです。 ●そして、なんと―― 『わたし探し・精神世界入門』の表紙の真ん中に赤でかいてある言葉… http://yoga-watashi.nay.jp/ Who am I ? ↓↓ 私とは、何か? ――というヨガと冥想の究極のテ−マが、 埴谷雄高(はにやゆたか)のテ−マのひとつであると知りました。  ●しかし、彼は、筋金入り(すじがねいり)の唯物論者(ゆいぶつろんしゃ)であり、 ヨガと冥想による『わたし探し・精神世界入門』の答と同じには、なりません。 ●彼の本名は、 仏教の悟りの知恵をあらわす般若(はんにゃ)と同じ 「般若(はにや)」です。 『般若心経』(『ヨガと冥想』90p 脚注)と同じ字です。 しかし、彼は、自分の本を書くときに、 その名は名のりません。 あえて「埴谷」と、 音は同じでも、 仏教的な意味をもたない姓にしています。 ●埴谷雄高は――吉祥寺(きちじょうじ)に住み、 井の頭公園の森↓を散歩しながら ――すでに死んでしまった、 たくさんの人たちが伝えたかった精神の声を聞き、 それらと対話しながら、 『死霊(しれい)』の構想を練り続けていたといいます  ●「私は、私である」というのが、 「自同律(じどうりつ)」 すなわち「同一原理」で、 論理学の基本です。 英語では princeple of identity いわゆるアイデンティティ。 私 = 私 A = A ●埴谷雄高は、 日本人として戦前に台湾で生まれ育ち、 過酷な占領者=支配者の側の人間として暮らし、 それがとてもイヤで、 「自分=日本人」であることがイヤ…になったそうです。 それが…「自分が自分であることが、イヤ」という 「自同律の不快」につながったようです。 ●後記;埴谷雄高氏は、「台湾」生まれでした。 「韓国で育ち」と書きましたが、お詫びして訂正します。2006年7月14日 ●「私とは、何か? = Who am I ?」 ――という問いは、 「自分が自分であることが、イヤ」という 「自同律の不快」があるからこそ、 始まるのではないでしょうか? ●自分(という存在)に疑いがなければ、 そんな問いは、うかばないでしょう。 たとえば、親からいただいた、 この体や顔や能力が…気に入らない…イヤ… 自分がイヤ…… 私 ≠ 私 A ≠ A 「(この)私」は、「(みんなが思っているような)私」では、ない。 すなわち、私 ≠ 私 ↓↓ 要するに、「私」は、「私」では、ない。 ●これは、論理学からいうと、おかしい論理です。 A = A でなく、 A ≠ A すなわち、「A は、 Aでは、ない 」といっているのですから。 ●だから、この問題は、 論理学というよりは、 文学(ぶんがく)や 芸術に かぎりなくちかづくテ−マなのです。 ●埴谷雄高が「難解」といわれるのも、 論理学の基本に挑戦した 「論理のアクロバット」にあるのでしょう。 ●知性で、判ろうとすると、わからない。 ●… でも、感性で、感じると、わかる。 ●『BIG ME』177p にかいたように 「犬になりたくなかった、犬、スヌ−ピ−の気持ち」は、よくわかります。 現代は、ス−ヌ−ピ−のように、 「犬でさえ、犬であることが、イヤ」な時代です。 そして、小さな子どもすら、 そんなス−ヌ−ピ−の感性を愛し、 世界的なキャラクタ−になっています。 ●「今、ここの、(小さな)自分だけが自分(ME)である…なんてイヤ」 ――「どこかに、輝く本当の自分がいるはず…」と感じて ――「自分探し」をしているひとが多い現代… 自分がイヤ……という「自同律の不快」は 、実は、今のひとたちにとても共感しやすいテ−マかもしれません。 ●イヤなままで終わらないために、 ヨガと冥想の方法と実践があり、 わたしの本やDVDやCDや、 NAYヨガスク−ルがあるのですが…… ●埴谷雄高は、「自分の血」を残すことを嫌い、 子をつくらず(奥さんはいろいろと大変だったようですが)、 「精神のリレ−」という言葉を残しています。 血ではなく、精神= spirit を マラソンのバトンタッチのように受け渡していく…ことを願っていました。 その精神= spirit が 「霊(れい)」であり、 ガイスト(ドイツ語の精神。幽霊=ゴ−スト)であり、 『死霊(しれい)』なのでしょう。 ●彼に共感し、 340p に『死霊』のことも書いたので、 『わたし探し・精神世界入門』を生前、埴谷雄高さんにお贈りしたのですが、 ルビのふり方を仏教的な「しりょう」とふってしまったので不快に感じられたのか、 世紀末の当時盛んだったオウム真理教のようにあやしいへんなやつの本と思われたのか、無視(むし)…されました…。 ●『死霊』は、箱に入ったメモなど、ラストまで構想はできているのに、 小説という形にするのがむづかしく、 戦後50年たっても未完成の進行形で執筆して、 ついに未完で、彼はなくなりました(1910〜1997)。 埴谷雄高が生涯をかけ、精魂(せいこん)をかたむけた精神のリレ−。 あの井の頭公園の下から上に噴き上げる噴水にかかった虹のように、 水辺と空、天と地を結ぶような、 精神の虹の架け橋は、できているのでしょうか? 埴谷雄高が受け継ぎ ⇒次に伝えようとした ⇒彼らの精神= spiritは、きちんと伝わっているのでしょうか? 精神のリレ−は、今、どうなっているのでしょうか? |
|||||||
|
|||||||
| ・ | |||||||
|
| ←★前へ | ●全バックナンバー● | 次へ★→ |
 トップページへもどる
トップページへもどる