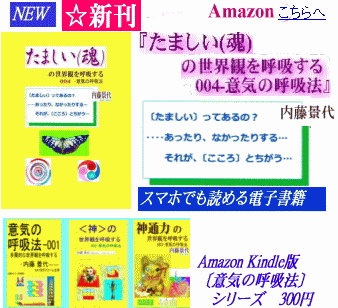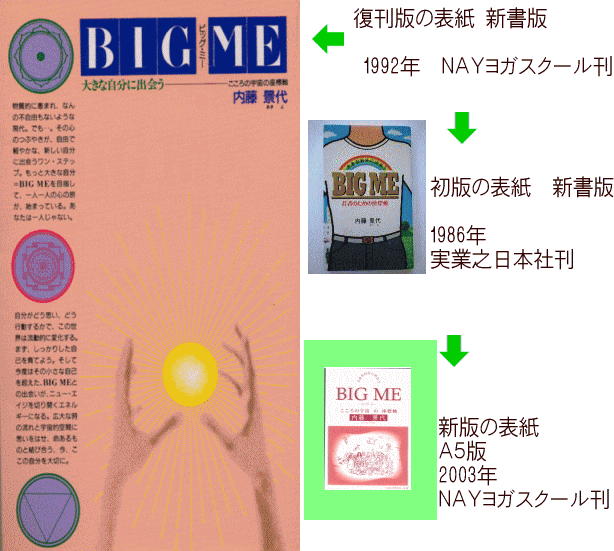2002年11月19日(火)
|
昨夜は、強い風が吹きました。 きのうかいた黄葉や紅葉のシ−ンは、 ずいぶんと変わってしまい、 そのかわり、赤や黄色、オレンジ、黄緑などの落ち葉が、 ふかふかのジュウタンのように、つちの上をおおっていることでしょう。 ●きのう、まぁるく、こんもりしていた、 ↓イチョウの木です。 きのうの風で、きょうは、どんな感じになっているでしょうか。  ●黄葉したイチョウの木 ●黄葉したイチョウの木金色の 小さき鳥のかたちして、 いてふ(イチョウ)散るなり 夕日の丘に 与謝野晶子(よさのあきこ) ●長く続く並木が黄葉して、 車道のわきに黄色いカ−ペットの帯が つながっているようにみえました。 お寺や神社の庭などでは、 落ち葉を、竹の「熊手(くまで)」で、 古風に、はいているのをみて、次のような想像をしました。 ●はいても、はいても、落ちてくる、 黄色い枯れ葉を、竹の熊手ではきながら、 江戸時代のひとは、次のように、 感じたひとも多かったのではないでしょうか。 「この黄色い落ち葉が、 黄金色の小判(こばん)だったら、いいなぁ〜」  ←●熊手と落ち葉 ←●熊手と落ち葉●それが、熊手で「福をかっこむ」 酉の市の熊手になったのかなもしれない …と思いました。 ちょうど、季節は秋、 落ち葉の頃の祭礼ですし、 熊手に飾られた紙の黄金色の小判↓が、 そんな連想をうみます… ●黄金の小判は、 「富の象徴」なのかもしれません。 小判は、現代なら紙幣になるわけです。 でも露骨すぎて、野暮(やぼ)になるためか、 紙幣のミニチュアは、熊手には飾らないようです。  ●酉の市の熊手の小判 とおかめさん↑ ●もともとは、竹の熊手に おかめさんのお面をつけたくらいのシンプルなものが、 酉の市の熊手で、江戸時代にだんだん、 華美になっていったようです。 ↑ ●最近、知りましたが、 東京・目黒の「大鳥神社」の酉の市も、 浅草と並び、江戸時代に始まったそうです。 おもしろいのは、 「熊手の使い道」や「象徴するもの」が、 ちがう点もあるのです。 ●目黒の「大鳥神社」のご祭神、 日本武尊(ヤマトタケルノミコト)は、 焼き討ちにあったときに、 熊手を武器にして草をなぎ倒し、 火を防ぎ、向火(むかえび)をもって賊を平らげた、といわれます。 熊手をもって火を防いだという神話から、 火難除けの神様と伝えられ、 現在も「江戸消防記念会」が、 酉の市に参拝祈願をされているそうです。 ●それだけでなく、目黒の大鳥神社も、 ●手を「熊手」のかたちにして、 おなかにつけ、うつ伏せで両足をあげるのが 「バッタのポ−ズ」です。行動力や、ヤル気がでてきます。 ※→「バッタのポ−ズ」は、『綺麗になるヨガ』 220p ●今、\100Shoop で、 中国製の「竹の熊手」を売っているので、 手作りの「福をかっこむ熊手」をつくると、 世界にひとつですし、楽しいかもしれませんね。 自分にとっての縁起物を満載(まんさい)したりして… 桜もみじの写真は、また明日。 |
| ←★前へ | ◎全バックナンバー◎ | 次へ★→ |
 トップページへもどる
トップページへもどる

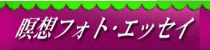
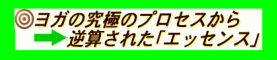 〔3時間で5,000円 〕会員は4,000円
〔3時間で5,000円 〕会員は4,000円