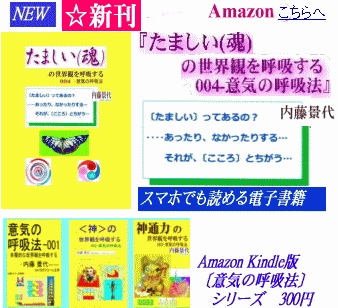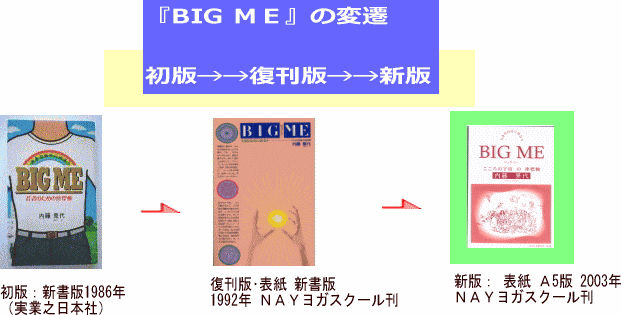| 2002年9月27日(金) ●100万本!の赤い彼岸花(ヒガンバナ)、別名は曼珠沙華(マンジュシャゲ)。●黄金色や白色の彼岸花。 ● 秩父の高麗(こま)と坂口安吾 | ||||||||||
秩父(ちちぶ)で、 100万本!の赤い彼岸花(ヒガンバナ) ――別名は曼珠沙華(マンジュシャゲ)――の赤いチカラに圧倒されました。 ……赤い花の群生(ぐんせい)の中での、 たった一輪の黄金色の彼岸花も、負けずに輝いていました。  ●オレンジがかった黄金色の彼岸花 ●自生(じせい)する真っ赤な彼岸花=曼珠沙華の群生↓ 想像を絶する数は、ハンパではありませんでした。   ●紅白(こうはく)の彼岸花  ●白い彼岸花↑ ●この秩父の奥の高麗(こま)の里に、 自生している「100万本の赤い彼岸花=曼珠沙華」の大軍の中では、 「白い彼岸花」は、ほんの少しでした。 けれども、はえているときは、必ず、数十本が集まってはえていました。 ●白い彼岸花は、東京でも、たまにみかけます。そういう場合は、必ず、紅白の彼岸花を、いっしょに植えてあるようです。 ●高麗では、赤い彼岸花を「曼珠沙華」とよんでいました。 赤い花は、「赤いトウガラシ・パワ−」にも通じるチカラを感じました。 この100万本!の赤い曼珠沙華=彼岸花は ――蛇行(だこう)して残された巾着(きんちゃく)の形をした土地の田 (=巾着田)が休耕地になって―― 自生し、地下茎で増え、群生したそうです。  ↑●西武線の高麗駅の前の2本の赤い柱。 ●西武線の所沢(ところざわ)の先、 飯能(はんのう)から2つ目の高麗駅をおりると、 呪術的な赤い2本の柱が、正面に立っていました。 ……どこかで見たことがある……と思いましたが、 新宿の韓国料理のお店の前に飾ってあった、 小さな2本の柱を3メ−トルくらいにした、迫力のある柱でした。 左は、「地下女将軍」。 …とかいてあり、それぞれの上に、 両目と口がかいてありました。 天と地、男性と女性、陰と陽の「対極のチカラ」の 「依り代(よりしろ)」として 、高麗の里を守ろうとする、韓国的な御柱(みはしら)なのでしょう。 坂口安吾が晩年のエッセイにかいていたので、 むかしから一度、来たかったところでした。 奈良時代から、 この里に、韓国の高麗(こうらい)のひと達が渡来し、 定住し、高麗(こま)という地名になり、 高麗川(こまがわ)も流れています。 高麗には、「高麗王(こまおう)・若光」の墓もあり、 安吾は、歴史のロマンを感じ、 想像力をかき立てられていたようです。 彼には、奈良時代を舞台にした『道鏡(どうきょう)』などの小説もありますし…。 ※→坂口安吾は、わたしの本、 『冥想 マインド・トリップ』 『BIG ME』や 『わたし探し・精神世界入門』などにでてきます。 巾着田(きんちゃくだ)という 曼珠沙華の自生地へ行く途中の家の前には、 「韓国のカボチャです」という紙がおかれ、 輪切りにしたカボチャや丸ごとのカボチャがおいてありました。 ↓ 日本の濃い緑のカボチャとちがい、 細長くて、つるんとしたベ−ジュ色でした。 まさにカボチャの異称の「唐茄子(とうなす)」という感じで、 ナス(茄子)を大きくしたような形でした。 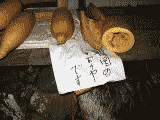 |
||||||||||
|
||||||||||
|
| ←★前へ |
|
次へ★→ |
 トップページへもどる
トップページへもどる

☆更新記録☆内藤景代・NAYヨガスクール関連サイト 最新のお知らせの記録

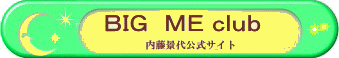
.gif)
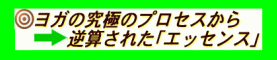




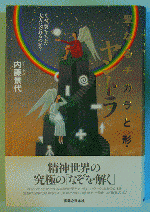

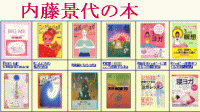
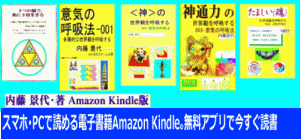
.gif)