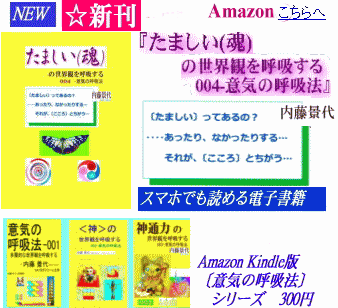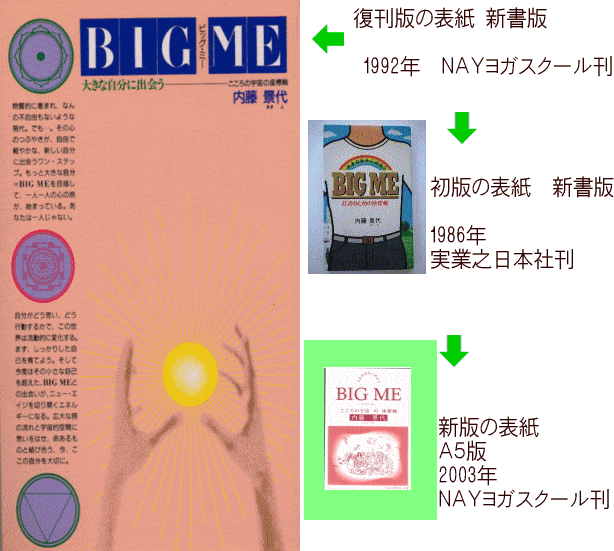| 2002年10月3日(木) 太鼓は、腰で打つ。腹に響く、井草八幡の大太鼓。 |
|
井草八幡(いぐさはちまん)神社の「大太鼓(おおだいこ)」は、直径が150cmくらいあり、野球のバットのようなバチ(撥)で太鼓をたたくのは、そうとうの修練が必要です。 その練習風景を、偶然、見たことがあります。 それで、「本番」の祭りが見たくて、↓きのう、出かけたわけです。 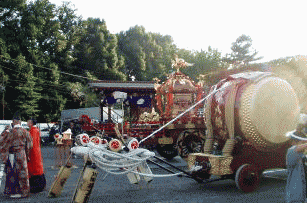 ●去年の秋、たまたま森林浴(しんりんよく)をかねて参詣(さんけい)した、 井草八幡神社で、だいの大人の男達が、かわるがわる順番に、 一所懸命に「大太鼓打ち(おおだいこうち)」の練習をしているのを見て、感心しました。 ●大きな木をくりぬき、牛の一枚皮(いちまいがわ)をはった、大太鼓。 倉からだされた、「新しい平成12年作の大太鼓」と神輿(みこし)が、台風の去った秋空に、輝いていました。大太鼓には「バチの痕跡」は残っていません。  ←●大正時代からの大太鼓 ●「大正時代からの太鼓」は、 長年、皮を叩いた茶色の痕跡(こんせき)が残り、 破れそうになってガラスの向こうに飾ってありました。 ●今、祭りで叩いている大太鼓は、新品なので、 まだ皮は固そうで、よい音色(ねいろ)を響かせるには、 腰を決めて、「井草八幡スタイル(?)」で、 構えて、全身で振り切らないと、うまくいかないようです。  ●面白いのは、 若くて力がありそうでも、 太鼓の音はうまく鳴らないことです。 50代、60代でも、 構えが決まっているひとは、腹に響く、 いい音をだします。→ ●野球スタイルや、武道スタイルなど、 各部門の力自慢(ちからじまん)らしい猛者(もさ)達が挑戦しても、 太鼓との喧嘩(けんか)や殴り合い(なぐりあい)ではないので、 太鼓はいい音色をだしてくれません。 肩に力が入っていない、 孫のいるような年配の男性が、 腰を決めて、聞き惚れる音色で叩き続けます。  ●太鼓は、腰で打つ。 腰のスワジスタ−ナ・チャクラと丹田(たんでん)がポイントです。 丹田力をきたえる、沖ヨガの道場では、直径50cmくらいの太鼓を打つことで、富士山の見える道場での生活の「時間の区切り」にしていました。  むかしの江戸城などでも、そうだったようです。 ※→丹田や沖ヨガ道場のことは、『こんにちわ私のヨガ』 ● 太鼓の音は、腹のマニプラ・チャクラに響きます。 太鼓の音を聞いていると、「腹がすわって」きます。 腹は、「内臓すなわちガッツ」のあるところなので、「ガッツ=根性(こんじょう)」も、でてきます。 「最近、粘りがないな〜」と感じたら、和太鼓の響きを聞くのもいいかもしれません。 ●とはいえ、ゲ−ムセンタ−で、今、人気の「2人で和太鼓を叩くゲ−ム」は、すこし、ハイ・ト−ンで、リズムが早すぎて、根性やガッツには、つながるかどうか…… 「ドラエモン音頭」とかにあわせても、いかがなものか…… あれは、盆踊り(ぼんおどり)の太鼓のノリのようです。 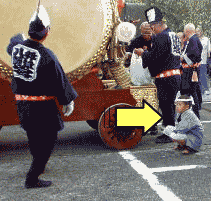 ←●大太鼓のそばから離れずに、ずっとしゃがんで、全身で響きを感じている少年。  ●「大太鼓」のそばにくっつくようにしてしゃがんで――いろいろな人の打つ太鼓の響きを――全身でずっと感じとっていた息子と、いっしょに帰る父(? たぶん親子さんでしょう…)。→ ●「奥多摩の獅子踊り」や 「大山阿夫利神社の神輿かつぎ」や、 この「井草八幡の大太鼓打ち」など、 古来からの祭りという非日常の時空間は ――ふつうの日常生活とはちがう―― 父たちの「かっこよさ」を見て、 若者や子ども達が憧れ、 「伝統の技(わざ)」を伝承(でんしょう)され、 継承(けいしょう)する時間・空間のように思います。 「技(わざ)という身体技法をともなう精神のリレ−の形」のひとつでしょう。 |
|
 ★#【電子書籍】内藤景代・著40サイトで新発売! #『幸せになれる! いつでもどこでも「瞑想」入門』 【電子書籍】で発売されました。 スマホ・パソコン・タブレットで読める【電子書籍】 |
|
| ←★前へ | ◎全バックナンバー◎ | 次へ★→ |
 トップページへもどる
トップページへもどる

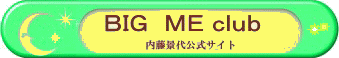
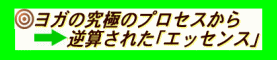




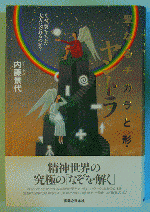



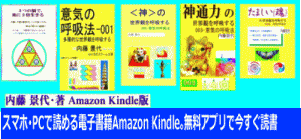
.gif)
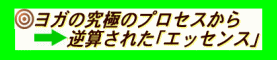 〔3時間で5,000円 〕会員は4,000円
〔3時間で5,000円 〕会員は4,000円