
| 2003年9月17日(水) ●廃墟は、アカマンマや猫じゃらし( エノコログサ)の原っぱに。●ままごと遊びの「アカマンマ(赤飯)」は、イヌタデ(犬蓼)。 ●オオケタデ(大毛蓼)は、1〜2m。 ●オオイヌタデ(大犬蓼)は、白いご飯粒のような花穂。 ●タデ(蓼)の花穂は、米粒のような花が開く。 ●白黒のゴマのように点がたくさんある、テントウムシ(天道虫)を、はじめて見た |
大きな空き地が、小さい家が並んでいた通りに、 急にあらわれ、向こうの通りまで見渡せるようになった夏の時季。 その頃は、茶色の土だけで、廃墟のようでしたが、 秋の今、アカマンマや 猫じゃらし( エノコログサ)などが一面にしげる、豊かな原っぱに変わり、 虫が鳴いています。 ままごと遊びで、「アカマンマ(赤飯)」に使った、 赤い花穂の「イヌタデ(犬蓼)」は、なつかしい草です。 ●お赤飯(せきはん)、 子ども用の言葉で「アカマンマ」は、 「おめでたいこと」があると、 お祝いに炊(た)く風習がありました。 今では、コンビニエンス・ストアで、 お赤飯のおにぎりが、毎日、売っていますので、 「めでたい」という気は薄れているでしょうが…… ●おめでたい、といえば、『家庭でできるビュ−ティ「ヨガ」レッスン』↓が、お陰さまで「8刷」になりました。 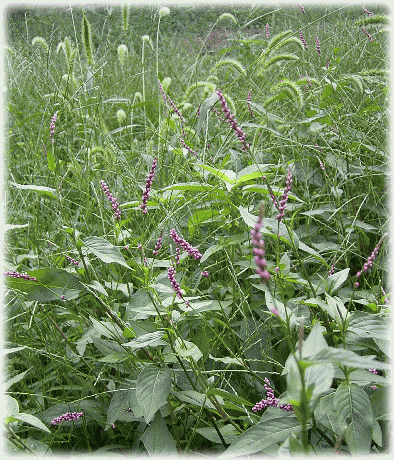 ●アカマンマ(イヌタデ 犬蓼)と、猫じゃらし(エノコログサ) ●注意して見ていると、 花の小さいものや大きいなもの、赤やピンク、 そして白い花まであります。 うちでは、「大きなアカマンマ(赤飯)」とか、 「白いアカマンマ(? ヘンですが)」で通じますけれど、 調べると、みな「同じ、タデ(蓼)科」で、名がちがうようです。 ●1〜2メ−トルほどの高さになる、 「大きなアカマンマ(赤飯)」とよんでいたものは、 「オオケタデ(大毛蓼)」です。↓ 「アカマンマ、別名をイヌタデ(犬蓼)」↑は、 赤い小さな花穂が上を向きます。 「オオケタデ(大毛蓼)」↓は、 花穂が重そうに下を向くものが多いです。 ●お赤飯の米粒(こめつぶ)に見立てた、赤い花穂。実は、花というよりは、開花前の「つぼみ」の集団でした。 小さな花穂のアカマンマ(イヌタデ 犬蓼)では、わかりにくいですが、大きなオオケタデ(大毛蓼)の花を拡大して撮影すると、米粒のような「つぼみ」と、開いた5弁の花が、よくわかります。下の右の写真です。白いオシベが、花から放射状に、はみ出ています。 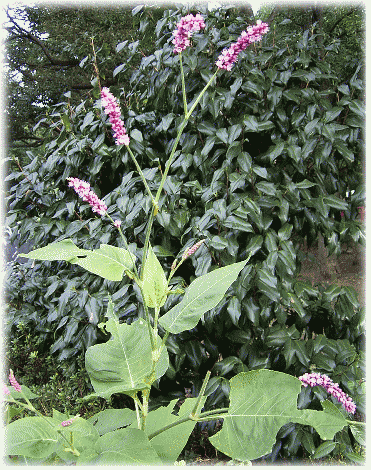 ●オオケタデ(大毛蓼)↑ つぼみと花↓  ●オオケタデ(大毛蓼)の花は、よほどおいしいのか、 花と同じくらいの小さな丸い虫が、 たくさん、花穂についていました。 まるで、お赤飯にふりかける 白と黒の胡麻(ごま)のような模様の、7mmくらいの虫。 近づくと、はじめて見るテントウムシ(天道虫)でした。 カブトムシ(甲虫)科のテントウムシは、点が2〜7あるのはよくみますが、このテントウムシは、黒地に白い点が、たくさんあります。↓ 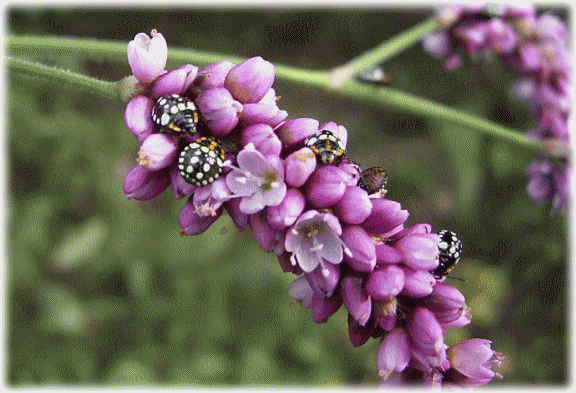 ●開花したオオケタデ(大毛蓼)に群がる、珍しいテントウムシ(天道虫)↑ 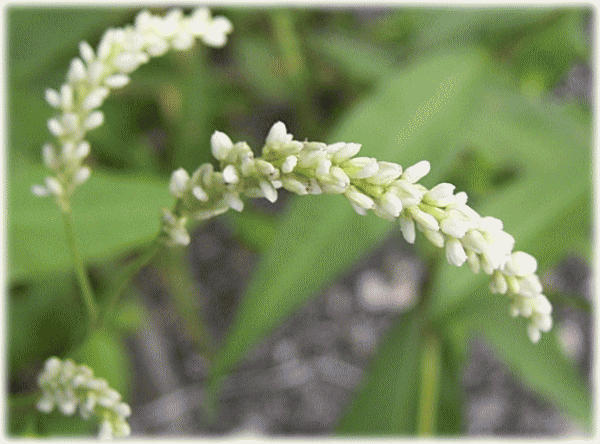 ●オオイヌタデ(大犬蓼)↑ ●「白いアカマンマ」というのは、ヘンですが、 「白いご飯粒(はんつぶ)」のような花穂のアカマンマ(?)が、 赤いアカマンマ(イヌタデ 犬蓼)の近くに、よくみかけます。 イヌタデ(犬蓼)すなわちアカマンマに似て、 それより大きいので、「オオイヌタデ(大犬蓼)」という名です。 オオケタデ(大毛蓼)のように、たれ下がります。 花の色は、淡いピンクから白。 ●オオケタデ(大毛蓼)の花は、中国原産で、 美しいと好まれ、江戸時代から、栽培されてきたそうです。 原っぱの、アカマンマ(イヌタデ 犬蓼)のそばには、 「秋の七草(ななくさ)」のいくつかが咲いていました。 けれども、現代人の感覚では、 「野草、すなわち雑草……、刈りとってしまえ」 という感じではないでしょうか。 「名のある、秋の七草」でも、 実物を見ると、「へぇ」というかもしれません。 知らずに、車で踏みつぶしていたりして…… そのうち、秋の七草の写真を、お見せしましょう。お楽しみに。 |
| ←★前へ | ●全バックナンバー● | 次へ★→ |
 トップページへもどる
トップページへもどる


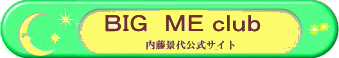
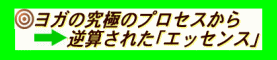






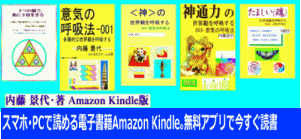
.gif)